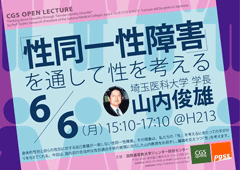ICU学部生 : 津島祥
【CGS NewsLetter 004掲載】
2005年6月6日、ジェンダー・セクシュアリティ研究の基礎科目の授業の一環として、埼玉医科大学学長の山内俊雄さんが「性同一性障害を通して性を考える」と題した講演を行った。山内さんは、1996年に、埼玉医科大学倫理委員会で委員長として、性同一性障害を医学的な治療対象とする答申を発表し、その後も日本精神神経学会で診断・治療ガイドラインの策定にあたり、日本における性同一性障害の治療に大きな貢献をしてきた。性同一性障害とは、自分が男/女であるという自己意識が、身体の生物学的性と一致しない状態にある疾患である。
2時間にわたる講演の中で、山内さんは、性同一性障害の成因とその日本での経緯、そして現状について説明した。性同一性障害の成因は、人の性の自己意識がどのように決定されるかという点を抜きには考えられない。この決定は、脳の形態や遺伝子によるとする説、社会的心理的要素から決まるという説など数説あるが、山内さんは、胎生時の性ホルモンによるという説が有力で、そのホルモンの異常が、身体の性と異なる自己意識が作られる原因ではないかという。
日本で性同一性障害を巡る状況が一変したのは1995年、それまで医学界においてタブー視されていた性別再判定手術の実施を望む医師が、その倫理性を問う申請を埼玉医科大学倫理委員会に提出したことがきっかけであった。このような倫理判断は日本で初めてであり、同委員会はこの問題についてまったく知識のない状態から勉強会を重ねて、翌年、性同一性障害を正式に医療の対象とするという答申を出した。山内さんは当時を振り返り、身体的な性と自己意識の食い違いで苦しむ当事者の状態を「疾患」と位置づけるべきかどうか悩んだが、医療の対象とするためには避けられないことであったとその葛藤を話した。
答申が発表されて以降、現在日本では日本精神神経学会のガイドラインに基づき、精神科医による診断、医療チームによる精神療法・ホルモン療法・手術といった三段階の治療が行われている。2003年には、当事者の強い要望と働きかけにより、当初には予想されなかったスピードで、性同一性障害を理由として戸籍上の性別記載を変更することを認める特例法が制定された。しかし、現行の法律は、子供がいないことが条件とされるなど当事者の実情に対応していない点も多い。性同一性障害を巡っては、他にも、専門家と医療機関の充実、保険が適用されない治療への経済的配慮、当事者や家族への支援、性別違和症候群への対応などの課題が指摘されている。
山内さんは、性同一性障害から更に話を広げ、男らしさ/女らしさについては、攻撃性や空間処理能力に関わる脳の構造的差異や性ホルモンによる機能的差異といった生物学的背景があり、そこに社会的文化的因子も加わり形成されていると説明した。そして、人の性は、生物学的性別、自己認識における性、性役割、性指向などのいくつもの側面から捉えられるものであり、従来考えられていたような男/女に二分されるのでなく、多様なあり方があるということが、性同一性障害の人たちから示唆されるとの見方を示した。
今回の講演を通して、性を巡る違和感が性同一性障害として名づけられ、医療の対象となったこと、そして、それが社会的に認知・受容されつつあることは、当事者にとって、Quality Of Lifeの向上につながる非常に大きな前進となったことがわかった。しかし、一方で私には疑問が残る。性同一性障害の概念とそれへの医学的・社会的対応は、一般的に、身体の性・性の自己意識・性役割が男/女という二元的な性別のどちらかにおいて一致するということを前提としている。そのことは、山内さんが指摘した「従来考えられていたような男/女に二分できない多様な性のあり方」を尊重することと相容れない側面があるのではないだろうか。
例えば、性同一性障害の人は自分の性器や身体の性的特徴に嫌悪感を持つとされている。その場合、当事者にはそうした身体の性的特徴を自己意識の性の身体へ近づける医学的な治療が提供される。ここで、身体の性と自己意識の性との間のずれをそのままにしておくのではなく、身体的性別を変えて自己意識の性に合わせていくという方向付けがなされるのは、「普通」は身体的性別と性の自己意識は一致するものだ、という前提があるからだろう。だが、当事者の間でも、どの程度身体の性を変えたいかについては、実際には意見に幅がある。性器は女性のまま胸の切除だけ行いたい人、社会的には反対の性を望んでも、身体は変えようと思わない人もいる。山内さんが、心の性での性器形成手術まで希望する人は当事者の1割程度だと話したことからも、当事者のすべてが自分の身体を自己意識における性と同性の人と同じようにしたがっているとは言えないことがわかる。そうした当事者の中の多様性は、ガイドラインにおいては尊重されるべきものとされているものの、特例法の整備においては十分に反映されておらず、戸籍の性別変更には「自己意識における性の性器に係わる部分に近似する外観を備える」という条件が付けられた。
また、性同一性障害が、身体的性別と反対の性としての性役割=自己認識における性の性役割を求める、と定義されているところから、自己意識における性と性役割の一致が前提とされていることがわかる。これは、例えば、身体的に男性でありながら自分は女性だという自己認識を持つ当事者ならば、子供のころから乱暴な遊びよりもままごとなど女の子の遊びを好み、成長してからも職場や家庭において、言葉遣いや身のこなしなどを女性的にすることを望むはず、という考えだ。しかし、身体的に女性であり、自分を女性だと思っている性同一性障害でない女性にも、こうした女らしさが自分には合わないと感じ、非女性的とされる役割を演じる人は少なくない。それを考えてみれば、心の性と身体の性が異なる人においても、性の自己認識とその人が望む振る舞い方が一致しているとは限らないはずだ。心の性は女性であり、身体的にも男性から女性になるような治療を望む人でも、性格は女らしくなく、スカートは履きたくない、なんて人がいても不思議ではない。けれど、心の性に社会が求める性役割を演じようとすることが性同一性障害の診断においては当然とされている。
そして、何より、性同一性障害における二元的な性別の捉え方は、私には性を巡る違和感を抱える人々の現実と矛盾したものに思える。性同一性障害の定義の中の「反対の性になりたいと望む」という言葉は、男/女が対になったものに二分されるという考えの上に出てくるものだろう。それでは果たして、どこまでが男でどこからが女なのだろうか。もともと女性器を持ちながら、ホルモン療法によって、その外観が男性器に近づいていた人は男なのか、それとも女なのか。現在の社会生活上は男性でありながら、子供にとって実母である人はどうなのか。自己意識の性と、服装や振る舞いなどは女性的であっても、体格などの理由から容姿が女性に見えない人はどうなのか。一口に性別に違和感を持つと言っても、一人ひとりの望みや落ち着くところの異なる性のあり方を、男/女に分けるのには限界を感じる。
このように、性別二元論や、身体と性の自己意識と性役割の一致といった考えの上に成り立つ、性同一性障害という「疾患」、そして、それを基盤とした医学的・社会的対応は、個々人の性の多様性を十分に受け入れきれない側面があると私は思う。性同一性障害中核群を中心に、医学的対応が可能になり、法整備が進んだことで、当事者が心の性における男/女のままで、社会に受け入れやすくなったことはもちろん喜ばしいことである。しかし、現実には、自己の性に違和感を持つ人たちは、必ずしも二元的な男/女への統合を目指すわけではない。そうした人々も含めて、一人ひとりの望む性のあり方を尊重していくには、まず、医学的・社会的対応において、山内さんも今後の課題とした、性別違和症候群という中核群以外の当事者への対応を充実させることが必要となるだろう。それと同時に、性同一性障害という問題に留まらず、さらに広く、性別二元論や、身体と性の自己意識と性役割の関係といった既存の性別に関する考えを問うことで、性の多様さが認められる社会的環境を整えていくことが重要なのではないかと思った。